はじめに|小さな子どもは「なんでも口に入れる」
乳幼児期の子どもは、身の回りにあるものを何でも口に入れてしまいます。これは「口唇期」と呼ばれる正常な発達段階の一部ですが、思わぬ事故につながることも。とくに怖いのが「異物誤飲(いぶつごいん)」です。
本記事では、子どもが異物を飲み込んでしまった際に取るべき行動、家庭でできる応急処置、受診の判断、予防法までを網羅的に解説します。
⸻
【結論】すぐに病院か救急車か、迷ったら「#8000」か「119」
まず結論から言います。
• 命に関わる危険があるとき → 迷わず【119番】
• 緊急性が判断できないとき → 【#8000(こども医療電話相談)】に電話
いずれにせよ、「様子を見ていたら大丈夫かもしれない」は命取りです。異物誤飲は“そのとき”の対応が、予後(回復)を大きく左右します。
⸻
よくある誤飲物と危険性
【1】ボタン電池|数時間で食道穿孔の恐れ
最も危険とされるのが「ボタン電池」。特にリチウム電池は、わずか2時間ほどで食道の粘膜を焼き、穴を開けてしまいます。これは命に関わる緊急事態です。
対応:すぐに救急車を呼ぶ。絶対に食べ物・飲み物を与えない。
⸻
【2】マグネット(磁石)|腸閉塞・穿孔のリスク
強力なネオジム磁石など、複数個を誤飲すると、腸内で磁力によって腸壁が引き寄せられ、壊死や穿孔を引き起こすことがあります。
対応:複数個の誤飲が疑われる場合は即受診。X線で確認を行う。
⸻
【3】たばこ・灰皿の水|ニコチン中毒の恐れ
たばこ1本でも、幼児にとっては命に関わるニコチン量。灰皿の水も同様に危険です。
対応:口にした場合は吐かせず、すぐに病院へ。
⸻
【4】薬(おとな用)|量次第では急性中毒に
親が服用中の睡眠薬・降圧剤・抗うつ薬なども誤飲リスクが高い。特にシロップ剤やゼリー剤は子どもが好みやすい。
対応:服薬量、時間、成分名を確認し、早急に医療機関へ。
⸻
【5】おもちゃのパーツ・ビーズ・硬貨
比較的多い事例ですが、形や材質によっては窒息や腸閉塞を起こすことも。特に直径2.5cm以上のものは危険。
対応:苦しそうなら即座に応急処置。そうでない場合も受診して確認を。
⸻
子どもが異物を飲み込んだときの対処ステップ
【STEP1】窒息の有無を確認する
• 苦しそうに咳き込む
• 声が出ない
• 顔色が悪い(青白い)
• 手を喉に当てる
これらがある場合は、窒息のサインです。すぐに以下の応急処置を行い、119番通報をしてください。
⸻
【STEP2】窒息時の応急処置
■ 乳児(1歳未満)の場合
1. 赤ちゃんをうつぶせに抱え、頭を下にする
2. 肩甲骨の間を5回、手のひらで強く叩く
3. 異物が出なければ仰向けにして胸部圧迫(2~3cm程度)
■ 幼児(1歳以上)の場合
1. 背中を強く5回叩く(背部叩打法)
2. 異物が出ない場合は腹部突き上げ法(ハイムリック法)を行う
※ただし正しい手技を理解していることが前提。怖ければすぐ救急要請
⸻
【STEP3】意識がある場合の観察ポイント
• 意識はあるか
• 泣ける・話せるか
• 嘔吐していないか
• 呼吸のリズムに異常がないか
「いつも通り」のように見えても、体内で危険が進行していることがあります。
⸻
【チェックリスト】受診の判断ポイント
以下のいずれかに当てはまる場合、今すぐ受診してください。
• ボタン電池、磁石、薬を飲み込んだ
• 窒息の兆候がある
• 呼吸が浅く苦しそう
• 嘔吐を繰り返す
• 出血(吐血・下血)が見られる
• 時間がたっても異物が排出されない
• 飲み込んだ物が特定できない
⸻
何科に行くべきか?
通常は「小児科」で対応できますが、状況により以下の診療科が対応します。
状況
推奨診療科
異物が気道にある疑い
耳鼻咽喉科
異物が消化管にある疑い
消化器外科、小児外科
誤飲後に意識障害やけいれん
救急科・脳神経科
⸻
子どもの誤飲を防ぐ5つの習慣
① 高いところ・鍵付きケースに収納
電池、薬、たばこなどは「見えない・届かない」が鉄則。
② おもちゃの選び方に注意
対象年齢の表示を守る。誤飲しやすい小さなパーツのないものを選ぶ。
③ 食事中は「ながら食べ」禁止
歩きながら・テレビを見ながらの食事は、のどに詰まりやすい。
④ 兄姉のおもちゃ・ビーズにも注意
年上のきょうだいのおもちゃから出る部品が誤飲リスクになるケースも。
⑤ 日頃から応急手当の講習を受ける
ハイムリック法・AED・CPRの基礎を親が身につけておくことで、大きな安心感に。
⸻
まとめ|迷ったらすぐ相談・受診を!
子どもが異物を飲み込む事故は、誰にでも起こり得ます。大切なのは、「落ち着いて正しく対処すること」。そして、少しでも不安があれば専門機関へ相談を。
日本中毒情報センター
072-727-2499(365日24時間)
編集後記|備えることは「愛」
「うちの子は大丈夫」と思わず、常に最悪を想定して備える。それが親の責任であり、愛でもあります。このブログが、少しでもお子様を守るヒントになれば幸いです。

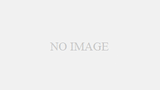
コメント