はじめに|防災で「栄養」は見落とされがち
地震、台風、大雨、噴火など、自然災害が頻発する日本では、防災グッズの備えはすでに「当たり前」になりつつあります。しかし、多くの家庭でまだ十分に整備されていないのが「非常時の栄養管理」です。
特に注目すべきは、タンパク質=プロテインの重要性。
被災生活では食料が不足しやすく、バランスの偏った食事になりがちです。パンやおにぎり、カップ麺など炭水化物中心の支援物資に偏る中で、タンパク質不足が深刻な健康リスクにつながります。
本記事では、「防災×プロテイン」という新しい視点から、災害時に命を守るための栄養管理術を徹底解説します。
なぜ災害時に「プロテイン」が必要なのか?
1. タンパク質不足は「免疫低下」と直結する
避難所や車中泊などの生活環境では、衛生状態が悪化し、感染症にかかるリスクが高まります。免疫を維持するためには、ビタミンやミネラルとともに、タンパク質が不可欠。
プロテインが不足すると…
- 傷の治りが遅くなる
- 感染症にかかりやすくなる
- 筋肉量が減り、体力低下
- 高齢者は転倒リスクが増大
つまり、命に関わる健康被害が起きかねないのです。
2. 被災生活では「調理しない・保存できる」栄養源が重要
タンパク質は本来、肉・魚・卵・大豆などから摂取します。しかし、被災時には冷蔵庫もガスも使えない状況が想定されます。
そんな中で、調理不要で長期保存できる「プロテインパウダー」や「高タンパク食品」は非常に有効です。
防災用プロテインの賢い選び方
✅ 1. 長期保存できるタイプを選ぶ
- 常温保存OKのパウダータイプ
- 保存料入りのプロテインバー
- 開封しやすくシンプルな包装が理想
➡【例】
- ザバス(SAVAS)
- ミルクプロテイン(ロングライフタイプ)
- INバー プロテイン(森永製菓)
✅ 2. 水がなくても摂れる形状が便利
断水時に備えて、**水不要で食べられる「バータイプ」「クッキータイプ」**は特に重宝されます。
- 噛み応えがあると咀嚼にもなり、満足感が得やすい
- 甘すぎない・チョコ味など嗜好性も大切
✅ 3. 家族構成・年齢に応じて調整する
- 子ども用は低カフェイン・低脂肪
- 高齢者には消化しやすい粉末タイプ・豆由来
- アレルギー対策が必要な家庭では大豆・乳不使用製品を常備
プロテインは「心のケア」にも効果がある?
被災直後の不安定な状況では、精神的ストレスや疲労から食欲が低下する人も多く見られます。
そんなときでも、甘めのプロテインシェイクやチョコレート風味のプロテインバーは、摂取しやすく「ホッとする栄養補給」として役立ちます。
特に高齢者や子どもは、体力・筋力の維持だけでなく、**精神的安定のための“安心食”**としても、プロテインが有効です。
実際に備えておきたい「防災×プロテイン食品」5選
商品名・特徴・保存期間
ザバス ミルクプロテイン(ロングライフ)
常温保存可・飲みやすい
約6カ月
INバー プロテイン(森永)
水不要でそのまま食べられる
約12カ月
大豆プロテイン(無添加パウダー)
植物性・アレルギー対策に◎
約12カ月
UHAグミサプリ プロテイン
グミ状でおやつ感覚
約12カ月
明治 SAVAS for Woman
女性や高齢者向けの栄養バランス
約8カ月
災害時の「1日タンパク質必要量」とプロテインの摂取量目安
一般的に必要なタンパク質は…
- 成人男性:約60g/日
- 成人女性:約50g/日
- 高齢者や成長期の子どもは+10gが理想
プロテインパウダー(1杯)=約15gのタンパク質
→1日2杯程度を目安に補給すればOK。
もちろん、これに加えて他の備蓄食品(缶詰・レトルト)で栄養バランスを取るのが理想です。
【体験談】災害ボランティアで気づいた「栄養」の大切さ
私が実際に参加した能登半島地震の災害ボランティアでは、避難所で高齢者が「おにぎりばかりで体がもたない…」とつぶやいていた姿が印象的でした。
確かに提供されるのは、炭水化物中心。おかずやタンパク質を摂る機会が極端に少なく、数日で体調を崩す人も出ていました。
この経験から、「プロテインを防災グッズに入れるべきだ」と強く感じました。非常時にこそ“体づくりの視点”が重要になるのです。
まとめ|非常時も“健康を守る備え”を
- ✅ 災害時はタンパク質不足になりやすく、体力・免疫が低下する
- ✅ プロテイン食品は「調理不要・保存性が高い」備蓄に最適
- ✅ 子ども・高齢者・アレルギー持ちなど家族に応じた工夫が必要
- ✅ 甘さ・食べやすさも心のケアにつながる
非常用持ち出し袋に水・ライト・ラジオと一緒に、**プロテイン食品を加えておくことで、命を守る“栄養の盾”**が一つ増えます。
最後に|あなたの防災袋、タンパク質足りてますか?
「生き延びる」だけでなく、「健康に避難生活を過ごす」ための備えとして、ぜひ**“プロテイン”を新たな防災習慣に加えて**みてください。

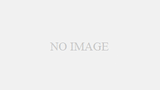
コメント